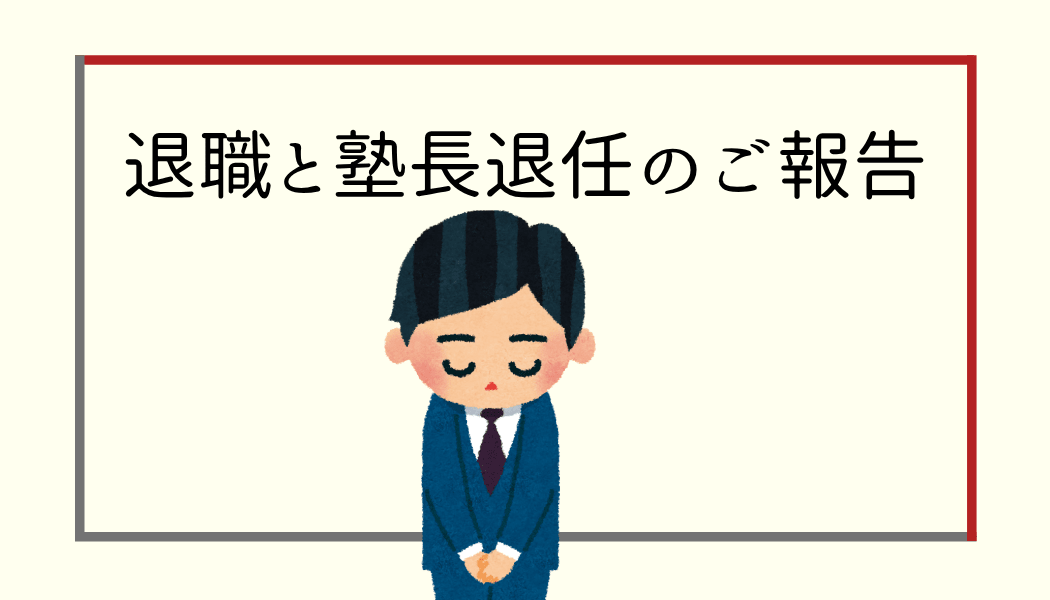自律神経の乱れ?子どもの不調に要注意!
講師ブログ
暑さが続く時期や湿度の高い時期、お子さまの体調はいかがでしょうか。眠れているでしょうか。
夏の暑さやエアコンによる体の冷え、夏休みなどで生活リズムが昼夜逆転したり、ゲームなどで交感神経が優位になりすぎたりすると、子どもでも自律神経の不調を起こしやすくなります。
今回は子どもの「自律神経の乱れ」についてお話ししたいと思います。
子どもの自律神経の不調が原因と考えられるサイン

■身体的症状■
|
・朝すっきり起きれない |
■精神的・行動的症状■
| ・無気力、気分の落ち込み ・イライラ、怒りっぽい ・集中力、記憶力の低下 ・不安感 ・学校に行きたがらない ・赤ちゃん返り、甘え ・人との関わりを避ける ・音や光に過敏になる ・自己肯定感の低下 ・自傷行為 |
子どもが自律神経の不調から起こると言われている病

①起立性調節障害
症状:朝起きられず午前中体調不良(倦怠感、めまい、立ちくらみ、頭痛、吐き気、腹痛)が続く。
顔色が悪かったり、食欲不振、動悸、息切れ、夜に眠れない、日中に眠気がきたりする。
学校に行けなくなる原因になりやすい病です。
➁過敏性腸症候群:脳と腸の連携の乱れが原因
症状:腹痛を伴う下痢や便秘、お腹の張りや吐き気など。
学校に行く前やイベントなど、ストレスや不安がかかる場面で症状が出やすいことがあります。
③睡眠障害
症状:不眠症、過眠症
④過呼吸症候群
症状:呼吸困難、胸の圧迫感、手足のしびれ、めまい、動悸、けいれんなど
子どもも心と体のストレスが溜まると自律神経のバランスが崩れ、弱っているところから壊れていってしまいます。
「朝になるとお腹が痛い」「トイレに行く回数が増える」「ぼーっとしてしまう」そのようなことが続く時は、「甘え」だとかと思わず不調のサインだと思ってください。
自律神経の不調に影響する要因
お子さんの不調のサインに気づくためには、まず日々の生活リズムを見直すことが大切です。
そして、どんな時に不調が起こりやすいか、お子さんの様子をよく観察してみてください。

幼いお子さん
特に幼いお子さんの場合、保育園、幼稚園、学校での緊張感や、親御さんから離れることへの不安が自律神経の不調の原因となることがあります。
また、ご家庭の生活スタイルに合わせて就寝時間が遅くなり、睡眠不足になっている可能性も考えられます。
さらに、家庭内の環境変化や親御さんの様子を敏感に感じ取り、それがストレスになっているケースも少なくありません。
幼いお子さんにとって、ご家庭が「安心できる居場所」であることは、心身の健康を保つ上で非常に重要です。

思春期のお子さん
思春期は、心や身体の急激な成長に伴い、自律神経が乱れやすい時期です。
この時期に自律神経の不調が目立つ背景には、いくつかの要因が絡み合っています。
特に注意したいのは、タブレットやスマートフォンの長時間利用による睡眠不足です。
また、水分摂取不足や運動不足も自律神経のバランスを崩す原因となりがちです。
適切な水分補給や身体活動は、自律神経の働きを整える上で欠かせません。
さらに、思春期は人間関係が複雑になり、勉強や将来への不安も増大する時期です。
学校生活や家庭でのストレスなど、緊張や不安が絶えない日々を過ごしているお子さんも少なくありません。
こうした精神的な負担が、心身症を引き起こし、自律神経の不調を顕著にさせる主要な要因となるのです。
改善方法

疾病教育
疾病教育とは、病気に関する正しい知識を習得し、病気との付き合い方などを学ぶことです。
身体が不調であるお子さんやその保護者がまずはその不調と向き合うことが大切です。
なぜつらいのか、身体に何が起こっているのかを知ることで不安が軽減され、お子さんに合った治療法も見つけていくことができます。

薬に頼らない療法
自律神経の不調を改善するために、薬に頼らずに取り組める方法が非薬物療法です。
これには生活習慣の改善、心理的アプローチ、代替療法など、さまざまな方法があります。
副作用のリスクが少なく、根本的な体質改善やストレスへの抵抗力を高めることにつながるのが大きな特徴です。
①規則正しい生活をする
・十分な睡眠時間の確保:できる限り決まった時間に寝起きし、安定した睡眠リズムを作りましょう。
・朝日を浴びる:朝起きてすぐに太陽の光を浴びることで、体内時計がリセットされ、自律神経のバランスが整いやすくなります。
・バランスの取れた食生活:
冷たいものや甘いものの摂りすぎに注意しましょう。身体が冷えすぎると自律神経のバランスが崩れやすくなります。
糖分の過剰摂取は、血糖値の急激な変動を引き起こし、イライラや集中力の低下、気分の波につながることがあります。
胃腸が弱いお子さんには「白湯」がおすすめです。体を温め、消化吸収を助ける効果が期待できます。
➁適度な運動を取り入れる
外で体をしっかり動かして遊んだり、太陽の光を浴びたりすることは、自律神経を整える上でとても大切です。最近では体を動かす機会が少ない子どもたちに「子どもロコモ(運動器症候群)」が増えています。子どもの頃の体づくりは、自律神経の健全な発達に非常に重要であることを覚えておきましょう。
③質の良い睡眠を確保する
睡眠中には成長ホルモンが分泌され、骨や筋肉の発達を促し、体内の修復や回復を進めます。また、日中に得た情報が整理され、記憶が定着するのも睡眠中の大切な働きです。質の良い睡眠は、心身の健康と成長に不可欠です。
④その他
・深呼吸(腹式呼吸)をする・ゆっくりと入浴する・音楽療法を試す・森林浴など自然に触れる
これらの方法を日常生活に積極的に取り入れてみてください。

おわりに
発達障害のあるお子さんは、特に環境からのストレスや感覚過敏によって、自律神経が乱れやすい傾向があります。
そこに人間関係や学習面でのストレスが加わることで、心身ともにバランスを崩し、不調をきたすことがあります。
だからこそ、私たち大人が不調を訴えるお子さんの特性や個性を深く理解し、寄り添うことが何よりも大切です。
まずは「わかってくれる人がいる」という安心感を与えてあげることが、お子さんの心を安定させる第一歩となります。
ストレスを完全に排除した環境を作ることは現実的ではありません。
ストレスには、心身に悪影響を与える「悪いストレス」と、成長につながる「良いストレス」があります。
また「頑張ってもどうしようもならないストレス」と「頑張れば乗り越えられるストレス」が存在します。
後者の「乗り越えられるストレス」を経験することは、自己肯定感を高め、成長と自信に繋がります。
体の不調で不安になっているお子さんへの適切な支援を通じて、健やかな成長を応援していきましょう。
個別指導塾にらいかない
塾長 久保田